
畳の歴史は日本の歴史
「畳」とは「たたむ」ことを意味し、折り返して重ねる意味でもあって、たためるもの、重ねられるものということから敷物全てを意味したものでもあり、これが「畳」という言葉の起こりであると言われています。
「畳」と言う言葉が使われた最も古い文献は、
「古事記」(太安麻呂撰・和銅五年 712年)中巻の、
「葦原の しけしき小屋に 菅畳 いや清敷きて 我が二人寝し」 (神武天皇)
「海に入りたまはむとする時に 菅畳八重 皮畳八重
きぬ畳八重を波の上に敷きてその上に下りましき」(景行天皇)
縄文時代 |
・竪穴住居にワラ敷きの跡 |
弥生時代 |
・ワラを薦コモ、筵ムシロ。つかなみなどに加工 |
古墳時代 |
・高床式住居で敷物、筵(ムシロ)、しとねの使用 |
飛鳥時代 |
|
奈良時代 |
・古事記の中に薦畳、皮畳、絹畳の記述 |
平安時代 |
・工匠としての畳技術者が出現 |
鎌倉時代 |
・書院つくりの普及、武家屋敷では寝所に畳が敷きこまれるようになった。畳から布団が分化する |
室町時代 |
・村田珠光が書院台子の式事を定めて珠光真の四畳半の茶室形式を始める。 |
戦国時代 |
・武家屋敷では寝所に畳が敷き込まれるようになった。 |
安土桃山時代 |
・綿ぶとんが普及し、町家や農村でも畳が敷かれるようになった。 |
江戸時代 |
|
明治時代 |
|
大正時代 |
・産業革命による都市への人口集中が住宅需要を拡大し、畳をより大衆化した。 |
昭和時代 |
・文化住宅化、和洋折衷住宅へと変わる。 |
平成時代 |
・超高層住宅の出現 |
| 畳張替え|ダイケン畳|たたみFAQ|畳チェック|畳と健康|畳と健康2|畳の歴史|こだわり柄畳 |

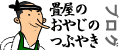
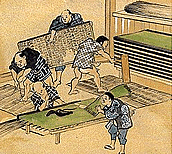 ・茶道の隆盛による畳の特殊化
・茶道の隆盛による畳の特殊化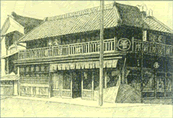 明治時代の畳店 安政2年(1855年)・文明開化に伴い家具調度の洋風化で畳の上に椅子が持ち込まれた。
明治時代の畳店 安政2年(1855年)・文明開化に伴い家具調度の洋風化で畳の上に椅子が持ち込まれた。